| 温泉の分類と効能 |
![]()
| ■温泉の定義と泉質の分類 ■新旧温泉分類比較 ■泉質名の表記方法 ■各泉質の定義および特徴 ■溶融成分濃度(浸透圧)による分類 ■水素イオン濃度(pH)による分類 ■源泉温度による分類 ■各泉質の効能 ■各温泉の効能(2006-07温泉シールラリー参加施設) ■源泉の利用方法 |
![]()
| ■温泉の定義と泉質の分類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「鉱泉分析法指針」では大まかに、以下の様に分類されている。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用語の解説
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※作成に当たっては、「アジア小僧がゆく ~ワシ的ケンキュウレポート温泉編~」 を一部参考引用しました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ページTOPへ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
| ■新旧温泉分類比較 | |||
| 新泉質表示 | 旧泉質表示 | ||
| 提示用新泉質名 | 新泉質名 | ||
| 単純温泉 |
- | 単純温泉 | |
| 二酸化炭素塩泉 | - | 単純炭酸泉 | |
| 炭酸水素塩泉 |
カルシウム・マグネシウム-炭酸水素塩泉
|
重炭酸土類泉 | |
|
ナトリウム-炭酸水素塩泉
|
重曹泉 | ||
| 塩化物泉 |
ナトリウム-塩化物泉
|
食塩泉 | |
| 硫酸塩泉 |
ナトリウム-硫酸塩泉
|
硫酸塩泉 |
芒硝泉
|
|
カルシウム-硫酸塩泉
|
石膏泉
|
||
|
マグネシウム-硫酸塩泉
|
正苦味泉
|
||
| アルミニウム-硫酸塩泉 | 明礬泉 | ||
| 含鉄泉 |
鉄(Ⅱ)-炭酸水素泉
|
炭酸鉄泉 | |
|
鉄(Ⅱ)-硫酸塩泉
|
緑礬泉
|
||
| 硫黄泉 | - | 硫黄泉 | 単純硫黄泉 |
| - | 単純硫化水素泉 | ||
| 酸性泉 | - | 酸性泉 | |
| 放射能泉 | - |
放射能泉
|
|
| 旧温泉法では右上の11種類に分類していたが、昭和53(1978)年「鉱泉分析法指針」の改訂により、温泉の泉質について新しい分類と呼称が定められた。これは温泉の泉質を、溶存物質総量及び特殊成分によって分類したもので、①単純温泉、②塩類泉、③特殊成分を含む温泉、④特殊成分を二種以上含む温泉、⑤副成分による塩類泉の細分類となっている。 ただし、温泉は実際にはこのようにキッチリ分けられず、温泉の中にはナトリウム-炭酸水素塩・塩化物泉(重曹泉+食塩泉)やナトリウム-炭酸水素塩・硫酸塩泉(重曹泉+芒硝泉)などのように、複数の泉質を併せ持つものも珍しくありません。 11PMの秘湯巡りでうさぎちゃんの温泉紹介に胸躍らせていた筆者にとっては、旧泉質名の方が馴染み深いですが・・・(笑) |
|||
| ※作成に当たっては、「ツムラ 温泉科学プロジェクト」 を一部参考引用しました。 | |||
| ページTOPへ | |||
![]()
| ■泉質名の表記方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 温泉に行くと、ホールや脱衣場などに必ず「温泉分析書」というものが、掲示してあります。コピーした紙切れもあれば、ご大層な額縁に入れたものまで様々ありますが、これは温泉法に基づく事業者の義務であり、掲示していない施設は法律違反となります。この温泉分析書には、温泉に含まれる成分の内容と量が記されており、これに基づいて泉質名が決まることになっています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【泉質名の記載方法のルール】 (ルール1) 陽イオン - 陰イオンの順に記載する。特殊成分がある場合は、先頭に記載する。 (ルール2) 各項目ごとに最も多い成分(主成分)を表記する。 (ルール3) 各項目間は、「-」(ハイフン)でつなぐ。 (ルール4) 主成分のほかに、構成比(mval%・mmol)が20%を超える成分がある場合、副成分として記載可能。 (ルール4) その場合、主成分と副成分を「・」(中点)でつなぐ。 (ルール5) 特殊成分は、含硫黄のように「含」をつける。 (ルール6) 特殊成分に硫化水素の形で硫黄を含む場合は、末尾に「硫化水素型」と表記する。 (ルール7) 特殊成分のうち水素イオンの場合は、含水素イオンではなく、「酸性」と表記する。 【泉質名の表記例】
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※作成に当たっては、「アジア小僧がゆく ~ワシ的ケンキュウレポート温泉編~」 を一部参考引用しました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ページTOPへ |
![]()
| ■各泉質の定義および特徴 | ||
| 単純泉 | 単純温泉 |
源泉温度が25℃以上で、温泉水1㎏中に溶存成分が1000mg未満のもの。ph(水素イオン濃度)が8.5以上あればアルカリ性単純温泉とも呼ぶ。含有成分が少ないため、刺激が少なく湯治向きで、所謂名湯と呼ばれる温泉が多い。 |
| 特殊泉 | 二酸化炭素泉 | 温泉水1㎏中に1000mg以上(鉱泉は250㎎)の遊離二酸化炭素を含み、溶存成分が1000mg未満のもの。泉温は問わない。泉温が上がると炭酸が気化して遊離するため、冷鉱泉や低温泉に多い。サイダーのように発泡するものが多く、別名「サイダー泉」とも呼ばれる。体内に吸収された炭酸ガスが毛細血管を拡張させるため、血圧降下作用がある。 |
| 塩類泉 | 炭酸水素塩泉 (重炭酸土類泉) |
温泉水1㎏中に溶存成分が1000mg以上のもの。泉温は問わない。主に陽(+)イオンのカルシウム(Ca2+)やマグネシウム(Mg2+)と陰(-)イオンの炭酸(CO32-)が結合。消化器系や循環器系の鎮静作用があり、飲用すると利尿効果もある。また石鹸があまり泡立たない。 |
| 炭酸水素塩泉 (重曹泉) |
温泉水1㎏中に溶存成分が1000mg以上のもの。泉温は問わない。主にナトリウム(Na+)と炭酸水素(HCO3-)が結合した炭酸水素ナトリウム(NaHCO3)、所謂重曹を主成分とするアルカリ性の温泉。皮膚の角質を乳化分解する作用があり、ヌルヌルした感触がする。一般的に「美人の湯」や「美肌の湯」とも呼ばれる。 | |
| 塩化物泉 | 温泉水1㎏中に溶存成分が1000mg以上のもの。泉温は問わない。主にナトリウム(Na+)と塩素(Cl-)が結合したもので、太古の海水が地中奥深くに封じ込められたものが多く、日本で一番多い泉質。舐めると当然のことながらしょっぱい。塩分が肌の保温効果を高め、湯冷めしにくいので「熱の湯」とも呼ばれる。 | |
| 硫酸塩泉 | 温泉水1㎏中に溶存成分が1000mg以上のもの。泉温は問わない。主にナトリウム(Na+)やカルシウム(Ca2+)、マグネシウム(Mg2+)と硫酸イオン(SO42-)が結合した硫酸塩を含む。動脈硬化の予防になるとされ、また飲むと苦味があり、糖尿病、痛風、胆石などに効果があるとされる。 ●ナトリウム-硫酸塩泉(芒硝泉)は軽い苦みがあり、動脈硬化や外傷に良いとされる。 ●カルシウム-硫酸塩泉(石膏泉)は、鎮静効果がある。 ●マグネシウム-硫酸塩泉(正苦味泉)は脳卒中の予防や後遺症に良いとされる。 ●アルミニウム--硫酸塩泉(明礬泉)は湧出時は無色透明だが、やや黄褐色になる。皮膚や粘膜を引き締める作用がある。 |
|
| 特殊成分含有泉 | 含鉄泉 | 温泉水1㎏中に20mg以上(鉱泉は10㎎)の総鉄イオンを含み、溶存成分が1000mg未満のもの。泉温は問わない。ヒドロ炭酸イオンと結合した鉄(Ⅱ)-炭酸水素泉(炭酸鉄泉)と、硫酸イオンと結合した強酸性の鉄(Ⅱ)-硫酸塩泉(緑礬泉)に大別される。湧出時には無色透明だが、空気に触れて酸化し茶褐色に変色するものが多い。保温効果が高く、造血作用を促すので貧血症に効果がある。 |
| 硫黄泉 | 温泉水1㎏中に2mg以上(鉱泉は1㎎)の総硫黄(硫黄(S)や硫化水素(H2S)など)を含み、溶存成分が1000mg未満のもの。泉温は問わない。卵が腐ったような独特の匂いがあり、火山地帯に多い。湧出時には無色透明だが、すぐに黄白色の沈殿物(湯の華)ができ、温泉らしさで人気がある。 | |
| 酸性泉 | 温泉水1㎏中に1mg以上の水素イオン(H+)を含み、溶存成分が1000mg未満のもの。泉温は問わない。ほとんどが無色か微黄褐色。硫化水素(H2S)、緑礬(硫酸鉄Ⅱ:FeSO4)、明礬(硫酸アルミニウム化合物)などを含み、酸性で匂いと殺菌力が大変強い。皮膚病、特に水虫や湿疹などの細菌性の疾患に効果がある。ただし刺激が強く、湯ただれを起こすことがあり、乾燥肌や高齢者・乳幼児には不向き。入浴後は真水で洗い流すのが良い。 | |
| 放射能泉 | 温泉水1kg中にラドン(気体)が100億分の30キュリー(=8.25マッヘ)以上(鉱泉は20キュリー)を含むもの。泉温は問わない。ラドンはラジウムから放出される安定希活性の気体(放射性同位元素:半減期3.8日)で、自然界に存在する物質中でもっとも強力なイオン化作用を持つ。肌や呼吸から体内に吸収されたラドンは、血液中のコレステロールや中性脂肪といった老廃物の代謝を活性化させる。 | |
| ※作成に当たっては、「温泉天国 温泉泉質別効能表」 を一部参考引用しました。 | ||
| ページTOPへ | ||
![]()
| ■溶融成分濃度(浸透圧)による分類 | ||
| 分類 | 溶存物質総量(g/㎏) | 人体の細胞液=約8.8g/㎏ |
| 低張性泉 | 8g未満 | 人体の細胞液に対して低い浸透圧 |
| 等張性泉 | 8g以上~10g未満 | 人体の細胞液に対してほぼ等しい浸透圧 |
| 高張性泉 | 10g以上 | 人体の細胞液に対して高い浸透圧 |
| 浸透圧とは、温泉成分が人体の細胞液への浸透し易さであり、高いほどよく浸透し効能が期待できる。日本の温泉の多くは中性から弱アルカリ性のため、低張性泉が最も多い。 |
||
| ページTOPへ | ||
![]()
| ■水素イオン濃度(pH)による分類 | |
| 分類 | pH度(水素イオン濃度) |
| 酸性泉 | pH3未満 |
| 弱酸性泉 | pH3以上~6未満 |
| 中性泉 | pH6以上~7.5未満 |
| 弱アルカリ性泉 | pH7.5以上~8.5未満 |
| アルカリ性泉 | pH8.5以上 |
| pH度が低いほど酸性に近づき、入浴時にヒリヒリする感じがする。またpH度が高いほどアルカリ性に近づき、皮脂を分解しお肌をスベスベにする。酸性が強いほど物質を溶かす力が強いため溶存成分も多く、アルカリ性ほど物質が沈殿し易くなるため、溶存成分が少なくなる傾向にある。日本の温泉は酸性泉は少なく、ほとんどが中性から弱アルカリ性の温泉。またpH10以上の温泉は、強アルカリ性泉とも呼ばれることがある。 |
|
| ページTOPへ | |
![]()
| ■源泉温度による分類 | |
| 分類 | 泉温(源泉の湧出時もしくは採取時の温度) |
| 冷鉱泉 | 25℃未満 |
| 低温泉 | 25℃以上~34℃未満 |
| 温泉 | 34℃以上~42℃未満 |
| 高温泉 | 42℃以上 |
| 温泉法では、湧出口での源泉温度が25℃以上か、特定の成分が一定量以上含まれているものを温泉と定義しており、25℃未満のものは冷鉱泉と呼ばれる。 |
|
| ページTOPへ | |
![]()
| ■各泉質の効能 | |||||||||||||||||||||
| 一般効能 | 泉質別効能 | ||||||||||||||||||||
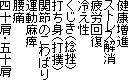 |
|||||||||||||||||||||
| 単純温泉 |
|||||||||||||||||||||
| 二酸化炭素泉 | |||||||||||||||||||||
| 炭酸水素塩泉 (重炭酸土類泉) |
|||||||||||||||||||||
| 炭酸水素塩泉 (重曹泉) |
|||||||||||||||||||||
| 塩化物泉 | |||||||||||||||||||||
| 硫酸塩泉 | |||||||||||||||||||||
| 含鉄泉 | |||||||||||||||||||||
| 硫黄泉 | |||||||||||||||||||||
| 酸性泉 | |||||||||||||||||||||
| 放射能泉 | |||||||||||||||||||||
| 一般効能は入浴時の温熱効果によるもので、血管が拡張して新陳代謝を高め、体内の老廃物の排出を促す。またぬるめのお湯は副交感神経を刺激し、リラックス効果がアップする。ただし42℃以上の高温浴は、血圧が上がり脈拍も増加するので、心臓病や高血圧症などの人は避けた方が良い。 泉質別効能は、温泉成分を肌から吸収また飲用することで、様々な薬理効果が得られる。 温泉の飲用については、所轄保健署署長の許可が必要で、年1回の一般細菌や大腸菌類の検査が義務付けられている。また温泉成分に含まれる重金属類(鉛・水銀・銅など)やヒ素などの含有量により、許容摂取量が定められている。最近の立ち寄り温泉のほとんどは、温泉資源保護や衛生上の理由から循環・ろ過・殺菌をしているため、飲用できない施設が多い。 |
| ※作成に当たっては、「信州の秘湯」 を一部参考引用しました。 |
| ページTOPへ |
![]()
| ■各温泉の効能(2006-07温泉シールラリー参加施設) | ||
| 単純温泉 | 飛騨古川桃源郷温泉ぬく森の湯すぱ~ふる | 四十八滝温泉しぶきの湯遊湯館 |
| ひだまりの湯 | 飛騨川温泉 しみずの湯 | |
| 南飛騨馬瀬川温泉 美輝の里 | 飛騨金山温泉 ゆったり館 | |
| 美濃白川スポーツ・スパランド | 天然 鷲ケ岳温泉 | |
| 牧歌の里温泉 牧華 | 明宝温泉 湯星館 | |
| 日本まん真ん中温泉 子宝の湯 | 関市上之保温泉 ほほえみの湯 | |
| 元湯 谷汲温泉 満願の湯 | 久瀬温泉 露天風呂 白龍の湯 | |
| グリーンハイツ養老 | 付知峡倉屋温泉 おんぽいの湯 | |
| くしはら温泉 ささゆりの湯 | 天然温泉 津島健康の里 湯楽 | |
| 稲武温泉 どんぐりの湯 | 天然温泉 クアハウス長島 | |
| 阿下喜温泉 あじさいの里 | 遊泉の郷 湯の山 片岡温泉 | |
| 糸生温泉 泰澄の杜 | ||
| 二酸化炭素泉 | なし | |
| 炭酸水素塩泉 (重炭酸土類泉) |
なし | |
| 炭酸水素塩泉 (重曹泉) |
ひらゆの森 | 飛騨にゅうかわ温泉 宿儺の湯 |
| ひだ荘川温泉 桜香の湯 | 厳立峡 ひめしゃがの湯 | |
| 湯の平温泉 | 個室露天・天然温泉 満天の湯 | |
| 美人の湯 しろとり | 関市武芸川温泉 ゆとりの湯 | |
| 関市板取川温泉 バーデェハウス | 池田温泉 本館・新館 | |
| 中津川温泉 クアリゾート湯舟沢 | 曽爾高原温泉 お亀の湯 | |
| 渓流温泉 冠荘 | ||
| 塩化物泉 | 天然温泉 白川郷の湯 | やまと温泉やすらぎ館 |
| うすずみ温泉 四季彩館 | 四季のふるさと養老 | |
| 南濃温泉 水晶の湯 | 安八温泉 保養センター | |
| 天然温泉 瑞浪の湯 たかさご | 長久手温泉 ござらっせ | |
| 天然温泉 みどり楽の湯 | げんきの郷 天然温泉 めぐみの湯 | |
| あいち健康の森温泉 もりの湯 | テルメ・ウツミ 白砂の湯 | |
| 天然温泉 かきつばた | 温泉 ラグーナの湯 | |
| 島ケ原温泉 やぶっちゃの湯 | みかた温泉 きららの湯 | |
| 花はす温泉 そまやま | 河野シーサイド温泉 ゆうばえ | |
| 越前温泉露天風呂 漁火 | 三国温泉 ゆあぽ~と | |
| 硫酸塩泉 | 佐野温泉 | |
| 含鉄泉 | 療養泉 八名温泉 | |
| 硫黄泉 | ひらゆの森 | 大白川温泉 しらみずの湯 |
| 今庄365温泉 やすらぎ | ||
| 酸性泉 | なし | |
| 放射能泉 | 美濃国 道三温泉 | バーデンパーク SOGI |
| 天然温泉 こまき楽の湯 | 猿投温泉 日帰り温泉施設 岩風呂 | |
| ページTOPへ | ||
![]()
| ■源泉の利用方法 | |
| 本来源泉100%をそのまま使用することが望ましいが、近年の温泉ブームで掘削したものも多く、温度が低い温泉もあるため、循環・ろ過・加温されているものが多い。 また公共施設としての温泉施設の場合、レジオネラ菌の繁殖を防ぐため、消毒されているもの多く、残念なことですが、100%源泉掛け流しの温泉はほんの一握りしかありません。 |
|
| 加水 | 源泉以外の水道水や河川水,地下水を加える。 ・源泉の温度が浴用には高すぎる場合,温度を下げるために行う。 ・湯量不足を補うために行う。 ・循環式浴槽の場合,浴槽内の湯が少なくなることを防ぐために行う。 |
| ろ過 | 源泉水や浴槽の湯に含まれるゴミなどを取り除く。 ・循環式浴槽の場合は必ず専用の装置で濾過を行う。 |
| 循環 | 浴槽の湯を再利用する。 ・湯量不足を補うため,湧出量に比べて浴槽が大きい場合に行う。 ・掘削した温泉の場合,後に湧出量が少なくなることを見越して行う。 |
| 消毒 | 殺菌のために,塩素系薬剤を加える。 ・循環式浴槽では必須。 ・近年はレジオネラ菌の増殖を防ぐために投入量が多くなる傾向。 ・紫外線やオゾンを使う方法もある。 |
| 加温 | 加熱して温度を上げる。 ・源泉の温度が低い場合(高温泉以外)に行う。 ・浴槽内の温度を一定に保つために行う。(特に循環式浴槽) ・源泉の温度が高い場合でも,掘削した温泉の場合,後に温度が下がることを見越して加温装置を設けておくことがある。 |
| ページTOPへ | |
![]()
